2025年、国民的牛丼チェーン「すき家」に起きた“ネズミ混入事件”は、飲食業界に衝撃を与えました。
SNSに投稿された衝撃的な動画によって「すき家 ネズミ」のワードは爆発的に拡散され、多くの消費者が怒りと不安を感じました。しかし、世間の印象とは裏腹に、すき家の業績は大きく落ち込むことなく、すでに回復傾向にあります。
「なぜすき家は倒れなかったのか?」
「企業の対応は十分だったのか?」
「すき家 ネズミ 犯人」として人手不足を疑う声は正しいのか?
この記事では、事件の経緯から企業対応、消費者心理、業績への影響までを一つ一つ丁寧に紐解き、“現代社会が飲食トラブルにどう向き合うべきか”を探ります。
「すき家 ネズミ」事件の概要と企業対応
すき家のねずみは誰かの仕込み感あるけど、あれは功罪という感じで、店内めちゃ綺麗になってて助かった
テーブル周りのベタベタとか注文用タブレットのベタベタとか床のペタペタとかだいぶ改善されててヨシ pic.twitter.com/yGhpJUqdbl
— たつきさんって暇なんですか? (@tatsuki1119) April 15, 2025
味噌汁にネズミが混入―発端はSNS動画
2025年1月、鳥取県の「すき家 南吉方店」にて、提供された味噌汁の中にネズミの死骸が混入していたという衝撃の事実が明らかになりました。
きっかけは、客が投稿した動画。この動画にはネズミの全体像がはっきり映っており、視覚的にも強烈なインパクトがありました。
-
SNSでは瞬く間に炎上、「#すき家ネズミ」や「#すき家ネズミ犯人」などのタグが多数出現。
-
ユーザーの間では「衛生管理が機能していない」「内部の犯行ではないか?」といった声が多く見られました。
-
類似事件への連鎖的な警戒も強まり、飲食チェーン全体に対する不信感が高まりました。
この騒動を受けて、すき家は極めて迅速に対応を行います。
全店一時閉鎖と営業短縮―すき家の対応は?
すき家を運営するゼンショーホールディングスは、事態の重大性を重く見て全国規模の緊急対策を実施しました。
一時閉鎖や営業時間短縮など、売上に直結する対策にも踏み切った姿勢が評価されています。
| 対応内容 | 実施期間 | 内容 |
|---|---|---|
| 全店一時閉鎖 | 3月31日〜4月4日 | 衛生点検・清掃強化のため、全国すべての店舗を一時的に営業停止 |
| 営業時間の短縮 | 4月5日〜当面 | 従来の24時間営業を23時間に変更。閉店後に清掃・チェック時間を確保 |
| スタッフ教育の強化 | 4月〜順次実施 | 衛生管理マニュアルの再徹底、監査頻度の増加 |
これは同業他社にも大きな影響を与え、「企業リスク管理の模範例」としても評価されています。
犯人は“人手不足”なのか?エキスパートの見解
SNSでは「すき家 ネズミ 犯人=人手不足」という意見が一気に広まりました。
しかし、チェーンストア研究家・谷頭和希氏はそれに対して冷静な視点を示しています。
「人手不足は要因の一部にすぎず、異物混入の件数自体は年々減少傾向にある。錯覚を生むのはSNSと報道の影響」
東京都の保健医療局のデータによると:
| 年度 | 異物混入苦情件数 | 備考 |
|---|---|---|
| 2015年 | 1,118件 | マクドナルド事件などが影響 |
| 2023年 | 546件 | 実数はむしろ半減している傾向 |
売上への影響が小さかった理由とは

「ネズミが出ても通う」圧倒的ブランド力と習慣化
2025年4月のすき家全店売上は前年同月比で約20%減。
一見すると深刻な数字ですが、4日間の全店閉鎖による13%減を除けば、影響はたった7%程度とも言えます。
では、なぜこれほど“軽微”に抑えられたのでしょうか?答えは、すき家がすでに生活インフラ化しているからです。
| 利用動機 | 説明 |
|---|---|
| 高コスパの食事提供 | 並盛350円前後、時間帯を問わず安定した満足度が得られる |
| 全国に展開された店舗網 | 駅前・郊外・住宅街など、あらゆる場所に点在しておりアクセス良好 |
| 利便性の高さ | モバイル注文、テイクアウト、深夜営業など現代ニーズに最適化 |
他チェーンとの比較―「マック事件」の教訓
飲食業界で異物混入が売上に与えるインパクトを考える上で、2015年のマクドナルド事件は避けて通れません。
| 企業名 | 異物混入内容 | 同月売上減少率 |
|---|---|---|
| マクドナルド | ナゲットに異物混入 | 約38.6%減 |
| すき家 | 味噌汁にネズミ | 約20%減 |
この差は、単なる事件の内容ではなく、ブランド信頼・顧客習慣・対応の速さが分水嶺となったと分析されます。
消費者が抱く“正しく怖がる”という感覚
すき家の一件が示したのは、恐怖の多くが「実数」ではなく「印象」で作られているという事実です。
-
異物混入件数は実際には減少傾向。
-
映像とSNSでの拡散力によって不安が増幅。
-
消費者の印象が先行し、実態との乖離が起きている。
専門家は「今後は正しく怖がる力が求められる」と指摘します。
つまり、企業の対応力・説明責任を冷静に評価できる視点を私たち消費者も持つべき時代に来ているのです。
まとめ:すき家はなぜ“潰れなかった”のか?
「すき家 ネズミ」問題は、日本中に“食の安全”への不安と関心を呼び起こしました。
しかし結果として、すき家は多くの消費者を失うことなく、危機を乗り越えています。
その背景には次のような要因が見られました:
・習慣的な利用による顧客の定着
・SNSによる炎上の本質と実数のギャップ
・“便利さ”と“信頼”が合わさったブランドの強さ
この事件は、飲食業界にとっては警鐘であり、消費者にとっては「情報との付き合い方」を見直す機会でもあります。
本当に見るべきは“起きたこと”よりも、“その後どう対応するか”。
私たちは今、企業と社会の成熟度が問われる時代を生きているのかもしれません。
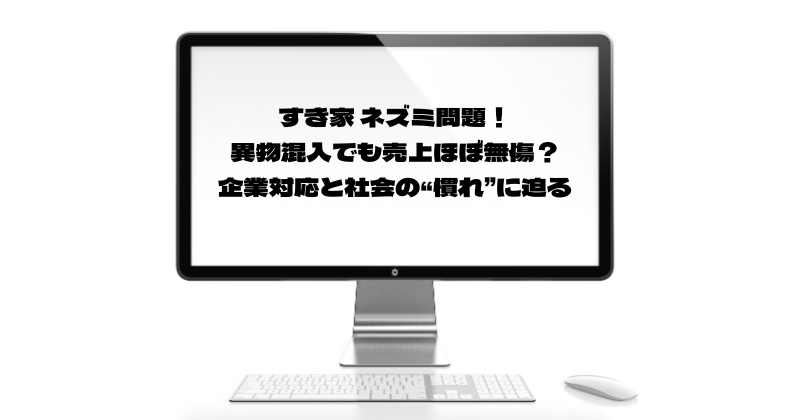


コメント